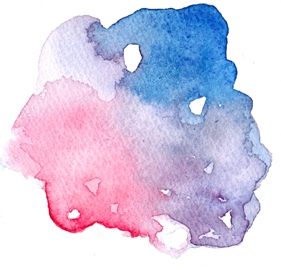
私は、美容師の父と母のもとに産まれた。
カットチェアに座ることがたまらなく好きな子供だった。
そこに座るだけで、なんだか自分が大人のように扱われている気がして、気分が良かったのだ。
母は髪を切る際、決まって
「可愛いちゃんになっちゃおうね」
と言った。
その赤ちゃんに話しかけるようなおどけた言い方がとても面白くて、私は無邪気に笑った。
鏡を通して見る母はどこか他人のように思えた。
母はそんな私の思いを見透かしたように、鏡越しに目が合うとにこっと笑顔を見せ、
安心させてくれた。
小学校高学年の時に父親が亡くなった。
突然のことだった。
担任の先生に職員室に呼び出され、事情を聞いた。
学校の外に出ると、親戚の叔母さんがタクシーの前に立っていた。
叔母さんはひどくおろおろとしていて、
「万梨子ちゃん……」
と声を出すのが精一杯のようだった。
大人でもこういう風になるんだ、と思った。
タクシーの座席はとても冷たくて、今でもその感触を思い出すことが出来る。
そのあとの空気は、すべてひんやりとしていた。
家に帰ると、真っ先にあったかいものが飲みたくなった。
コーンポタージュを飲み干すまで、私は生きた心地がしなかった。
あまりに急いで飲んだため、マグカップの底には粉末が固まって残っていた。
スプーンで崩すと、ぼろっと粉が出てきた。
少し舐めると、とても濃い味がして、1日に起きたことがフラッシュバックして溶けた。
お葬式の会場は抹香臭かった。
叔母さんに、この臭いはなに、と聞くと、
「それは樒よ。すごく綺麗な白い花を付けるのだけれど、猛毒があるのよ」
と教えてもらった。
この頃には母も大分落ち着いてきて、普通に受け答えが出来るようになっていた。
そんな母を横目に見ながら、私は意味も分からず、弔問客に頭をぺこぺこ繰り返し下げていた。
諸々のことが終わると、母は、
「どこか遠いところに行っちゃおうか」
と言った。
私は、お母さんと一緒ならいいよ、と答えたと思う。
ほどなくして、叔母の知り合いが運用しているマンションに、
母と2人で住まわせてもらうことが決定した。
百合ケ丘、というところに住むらしかった。
私もその付近の中学校に進学することが知らないうちに決定していた。
生まれ育った故郷を離れることは少し心苦しかったけれど、母と一緒なので寂しくはなかった。
母は鋏を仕舞って、新しく水商売を始めた。
お店に行くと、カランコロンとドアベルが鳴った。
家族でワークショップに行った時に、私が作ったものだ。
不格好ながら、父も母も大変気に入ってくれていて、嬉しかった。
――大きく書かれた『まりこ』という文字だけは未だに恥ずかしいけれど。
母はお客がいない時には、玄関を見つめていることが多かった。
どこに焦点が合っているか分からない母に、私は話しかけることが出来なかった。
しばらくすると、母はこっちの世界に帰ってきて、
「あら、帰ってたの。ただいまくらい言いなさい」
と言った。
ただいまと言わなきゃいけないのはそっちじゃないの、と言いたい気持ちはぐっと堪えた。
いつだったか母に、なんで人は生まれるん、と聞いたことがある。
その時の母がなんて答えたかはもう思い出せないけれど、
眉間に皺を寄せ、とても悲しい顔をしていたことだけは覚えている。
私はしまったと思った。
考えなくてもいいことは考えないようにしよう、それから私はそう生きている。